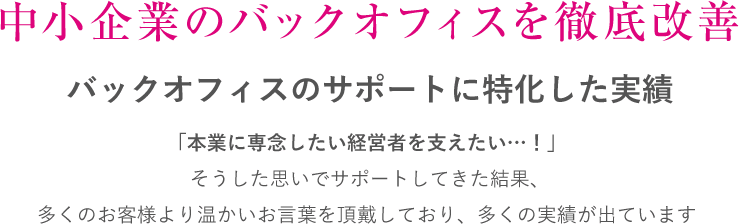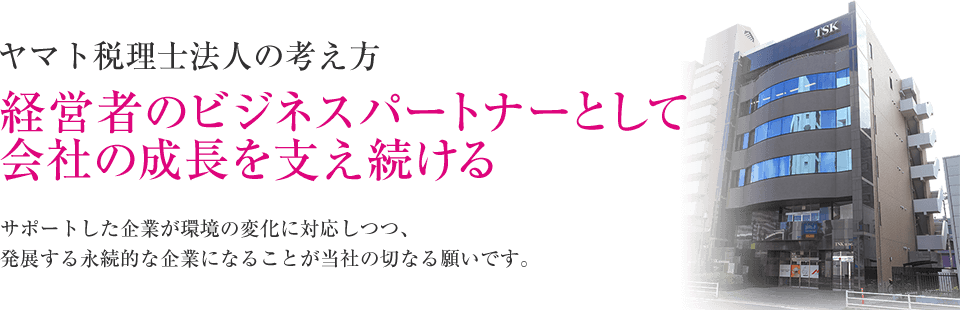株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました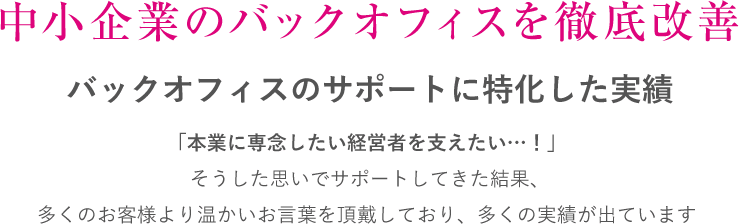

電子帳簿保存法は、1998年に施行された法律で、正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言います。
従来、会計帳簿や決算書といった書類は、紙での保存が基本でしたが、各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たせば、電子データによる保存を認めることを定めた法律で、事務処理負担の軽減を目指しています。
コロナ禍において、経理業務におけるDX化、デジタル化による効率化を急速に推進する必要性が出てきました。
下記にて、今回の改正でどのような点が大きく変更となっているかの4つのポイントをお伝えします。
①承認制度の廃止
②タイムスタンプ要件の緩和
③適正事務処理要件の廃止
④検索要件の緩和
以前よりも電子帳簿保存法の運用がされてきた中で、導入企業の少なさが最大の課題として挙げられてきました。
今回の法改正により、導入企業数増加の足枷となっていた承認制度の廃止により、より多くの企業に活用されることが期待されます。
電子データ保存を推進しようと試みていた企業の担当者にとっても、事前準備に関する労力や時間を大幅に削減できることは大きなメリットとなります。
タイムスタンプとは、電子的な時刻証明書のことを指し、電子データが作成された日時を確定することを目的とします。
従来まではタイムスタンプの付与を受領(署名)後の3日以内に行う必要がありましたが、対応期間を最長2ヶ月以内に延長したことで、担当者の余裕を持った対応が可能になりました。
今までの電子帳簿保存法では、不正防止を目的とし、厳重な社内規程を整備しておく必要がありました。
また、電子データの事務処理に関しても、厳重なチェック体制と定期的な確認が必要でした。
これらの厳しい内部統制の要件に関し、企業側にとって電子データ保存を導入する上での大きな課題となっていたため、チェック体制の緩和や原本の即時破棄は、ペーパーレス化の推進に繋がるでしょう。
電子データを保存する際は、必要なタイミングで内容閲覧、データ管理ができるように検索機能を備えておく必要があります。
一方、検索要件が細分化されていることで、登録や管理業務が煩雑になる傾向があります。
従来までは範囲指定や項目を組み合わせて設定できる機能の確保が不可欠であったため、各要件が複雑なことで導入障壁が高くなっていたことが課題でした。
上記でお伝えした通り、今回の電子帳簿保存法の改正に伴い、電子帳簿保存導入のハードルはとても下がりました。
次に、法改正に伴う現場の混乱を回避するためにも必要となってくる、中小企業が事前に準備しておくべき各ポイントをお伝えします。
①電子帳簿保存法の電子保存の対象となる帳簿・書類を把握する
②電子化の方法・方針を検討する
③不正防止の内部体制を整える
④いつでも相談できる専門家を見つけておく
電子帳簿保存法は大きく下記の3つに分類が可能です。
①自社で作成する国税関係帳簿書類
②取引先から紙で受け取る書類
③自社及び取引先で電子的に授受する書類(2022年1月1日より義務化)
3つの分類が可能ですが、2022年1月に施行される法改正により新たに義務化されるのが「③自社及び取引先で電子的に授受する書類」の分類となりますので、自社にて事前に対応できる体制を整えておく必要があります。
まずは請求書等に関するデータ書類の保存ルールは整っているか等、自社及び取引先で発生可能性の高い身近な書類よりルール整備をしていく必要がございます。
2022年1月に施行される法改正により、署名が不要になったり、タイムスタンプ要件の緩和によって、全社員が使うシステムに係る各データの電子化が可能になりました。
別途、電子化が可能がなりましたが、実際に対応可能なシステムを自社に導入するかどうかは慎重に検討する必要があります。
理由としては、システムを導入するとなると、当然導入費用、業務プロセスの見直しコスト、社員の教育コスト等が発生してくるためです。
しかし、従来通りの紙資料で各申請を行い、経理部門などでスキャナーによる一括電子データ化も認められています。
以上より、自社に合う適切な対応方法・方針をとるようにしましょう。
2022年1月に施行される法改正により、要件緩和と併せて不正に対する罰則が強化されました。
上記より、今回の法改正を機に電子帳簿保存導入を行う際には改めて不正防止の仕組み作りや体制強化が必要となります。
電子帳票保存の導入は、全社的な取り組みとなります。
ですので、経理、税務、システム、内部統制の各視点など、慎重に検討しなければいけないことが数多くあります。
また、とりあえず対応可能な‘システムを導入すれば何とかなる、といった安易な考えでは後々社内の混乱を招くリスクも増大します。
このようなリスクを極力抑えるためにも、電子帳簿保存導入を実施される際は、信頼でき、いつでも相談できる専門家を見つけておくことが重要となります。
相談先として考えられるのは、電子帳簿保存対応サポートを実施されている税理士やコンサル会社、システム会社が挙げられます。
上記にて相談先の候補を挙げさせていただきましたが、税務調査時に寄り添ってサポートしてくれるといった観点から、対応可能な税理士に依頼することが無難かもしれません。
弊社では中小企業の電子帳簿保存法対応を円滑に遂行するための各サポートを実施させていただいております。
具体的には、下記内容のサポートをさせていただいております。
弊社は経理業務改善に関する多数の実績を持つ専門家でございます。
今すぐ電子帳簿保存法対応を実現させたい、とお考えの企業様はまずは無料相談をご利用ください。
当社は、電子帳簿保存対応サポートを積極的に実施しています。
電子帳簿保存対応サポートに関する無料相談を実施しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください!